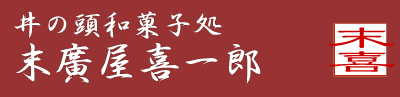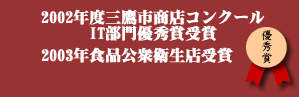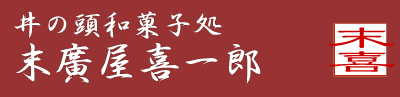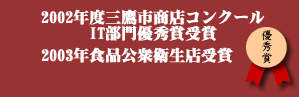鏡餅のお飾りの仕方。お飾りの意味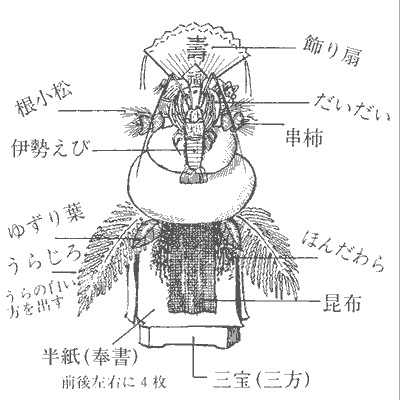
 鏡餅の上になぜ「みかん」をのせるのでしょう? 鏡餅の上になぜ「みかん」をのせるのでしょう?
鏡餅の上に「みかん」をのせますよね。
では、なぜ「みかん」をのせるのでしょう?
鏡餅の上にのせる「みかん」は、正確に言うと「ダイダイ(橘;たちばな)」と言います。ダイダイ(橘)は、お菓子の神様と言われている「田道間守命(たじまもりのみこと)」が、当時の第11代垂仁天皇のために、不老長寿の薬を求めて中国に渡り、そして持ち帰った不老不死の霊果です。つまり生命再生のサポートをする意味があるのです。
また、その他の飾りとして、「ほんだわら」や「ユズリ葉」「ウラジロ」などがあります。
「ほんだわら」とは、玉藻(たまも)のことでです。身がタワラの形をしているので「ほんだわら」といいます。玉藻は海の中で沢山の気泡をつけます。古代の人は、そこに海の生物の霊が寄り付いていると考え、「タマモ」と呼びました。この「タマモ」を正月に飾ることには、年神様の神霊によって海の魚たちが生まれ変わり、大漁の年になることへの願いが込められているのです。
島国の日本らしい風習ですね。大漁を直接願わずに、魚が生まれ変わることを願う日本人のこのような文化は、個人的に大好きです。
餅の下にユズリ葉を敷く。これも正月祝いという生命再生儀礼にふさわしいからです。
秋になると多くの広葉樹は枯れるのですが、ユズリ葉は枯れません。翌年「子の葉」が伸びて、さらに翌々年「孫の葉」が伸びてから、最初の年の葉が枯れ始めるのです。
つまり、ユズリ葉は三代も続く葉ということで、生命の永続性を象徴するのです。
特に、鏡餅の上にのせるダイダイと連れ立って、孫代々(ダイダイ)の譲り葉という言葉が生まれ、子々孫々まで繁栄する縁起物となったのです。
最後に、ウラジロですが、これは、シダの葉のことで、葉の裏が白いからこのように呼びます。日本民族は「清め」を最大の価値と考え、神は「清め」そのものと考えられていました。だから、神事には、常に白を多用するのです。そして、どこでも取れる白い葉の植物がシダだったのです。
つまり、鏡餅のコンセプトは、「新しい生命」。お飾りも全てこのコンセプトにのっとって、新しい命をサポートしているのですね。
鏡餅も何気にチームワークなのです…
▼感想はこちらまで。suehiro@sueki.jp

|